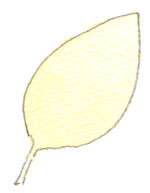|
ぬり絵 販売
塗り絵 無料ダウンロード 制作サービス インフォメーション
|
水彩画ぬり絵の描き方講座:水彩技法「ぼかし・滲み」初心者の方もやりやすい「ぼかし」、「滲み」の描き方をご紹介します。 水彩技法「ぼかし・滲み」をやってみよう!画用紙を水で濡らした状態に、上から濃い目の絵の具を筆でおいていくと、絵の具の濃いところから水だけの薄い部分にじわっと色が滲んでいきます。これを「ぼかし」や「にじみ」といい、水彩画の特徴的な技法になります。 画用紙に「ぼかし・滲み」を試してみましょう
鮮やかな落ち葉を「ぼかし・滲み」で描いてみよう!
さっそく水彩画ぬり絵 お花・植物画シリーズで試してみましょう! |
①各ページのご注文フォームまたはEメールにてご注文ください。
②ご連絡先メールアドレスに確認書が届きます。
③銀行振込にてお支払いただきます。
④ご注文の確定・発送させていただきます。
(※ ご入金の確認が出来た時点で発送させて頂きます。)
お支払方法が商品代引の場合
①各ページのご注文フォームまたはEメールにてご注文ください。
②ご連絡先メールアドレスに確認書が届きます。
③ご注文の確定・商品代引にて発送させていただきます。
④確認書内に記載された料金を商品到着時に宅配業者にお支払いください。(※ 代引手数料390円はお客様にてご負担頂きます。)
お支払方法でクレジットカードをご希望の場合
Yahoo!ショッピング「水彩画ぬり絵通販」をご利用ください。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nurie-tsuhan
注文受付完了から3~7日営業日みておいてください。
注文が殺到したり、宅配業者の事情によっては予定より遅くなる場合もあります。納期には余裕を持ってご依頼ください。
メールアドレス:info@suisai-tsuhan.com

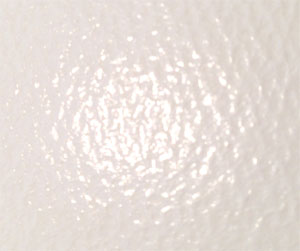
 次に筆で絵の具を少し濃い目に溶き、濡れた画用紙の上にトンとおくように絵の具をたらしてみましょう。
次に筆で絵の具を少し濃い目に溶き、濡れた画用紙の上にトンとおくように絵の具をたらしてみましょう。